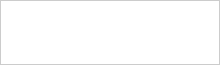25年春夏「輸入肉マーケットの動向」
めまぐるしく変化する外部環境に左右されやすい輸入肉であるが、最近の消費動向について畜種ごとに確認していく。
- 輸入牛肉の動向
農畜産業振興機構のデータによると、令和5年度(2023年4月~2024年3月)の日本の牛肉輸入量は50万1,898トンで、前年度比10.8%減少している。
特に米国産牛肉の輸入量は9万1,077トンと、前年度比19.3%の大幅に減少
。一方、豪州産牛肉の輸入量は9万2,972トンで、前年度比19.8%増加し、米国産と豪州産の輸入シェアが逆転した。
(出典:alic令和5年度の食肉の需給動向についてhttps://www.alic.go.jp/joho-c/joho05_003252.html?utm_source=chatgpt.com)
米国産牛肉の価格高騰は、円安や米国内の供給減少が主な要因と考えられる。
2024年5月の米国産牛バラ肉の国内卸売価格は、前年同月比約60%高の1キロ当たり1,436円となり、1993年の統計開始以来最高値を記録した。 - 輸入豚肉の動向
2023年度の日本の豚肉輸入量は、前年度比5.2%減の91万4,511トンとなり牛肉同様に減少傾向。
内訳を見ると、冷蔵品は39万2,732トン(同0.2%増)でほぼ前年並みで、冷凍品は52万1,652トン(同9.0%減)と大きく減少している。
主要供給国別では、カナダ産が18万1,233トン(同4.3%増)で全体の46%を占め、米国産は16万9,811トン(同8.9%減)で43%のシェアとなり、順位が入れ替わった。
メキシコ産は8万2,405トン(同12.8%減)で全体の16%を占めている。 - 輸入鶏肉の動向
近年、健康志向の高まりや中食需要の増加を背景に、安価で手軽なたんぱく源としての需要が拡大している。
特に、共働き世帯の増加やライフスタイルの多様化により、調理済みや簡便調理可能な鶏肉製品の人気が高まっていると考えられる。令和4年度の鶏肉の輸入量は、ブラジルが全体の73%、タイが25%となっており、日本のほとんどの輸入鶏肉はブラジルが担っている。
日本の鶏肉の需給では、国内消費の約25%が輸入鶏肉で、外食が中心であるものの、量販店でも経済メニューに注目が集まっているため、味付け肉やミート惣菜などの即食品での、鶏肉の需要が高まっている。
夏場の最需要期に向けた各畜種のポイント
【輸入牛肉】
例年以上に相場動向と政策の影響を見極めた売場戦略が求められる。
特に、「米国産・豪州産牛肉」の相場動向や乱高下する為替、さらにはアメリカの政権交代に伴う関税の変化が大きなカギを握ると考えられる。
米国産牛肉については、引き続き供給不安とコスト高が価格を押し上げると考えられる。
飼料価格や人件費の高騰に加え、トランプ大統領の政権復帰により、対日輸出への関税見直しによる、仕入れ価格の影響は無視できない。
2024年には「TPP11」による関税引き下げ効果により一定の価格競争力を保っていた米国産牛肉であるが、2025年はこのアドバンテージが失われる可能性がある。
昨年と同様の感覚での販売方法では無く、商品化にも付加価値を付けるような工夫が必要となると考えられる。
また、「ドル円為替」が引き続き「円安」基調にある点にも注意が必要。
輸入牛肉全体の価格が上昇傾向にある中で、単なる価格訴求では消費者の購買意欲を刺激できない場面も増えるため、提案型の訴求が求められる。
例えば「焼くだけ簡単 下味つけ込み済み焼肉」「タイパに最適レンジで簡単調理」など、わかりやすい商品コンセプトを打ち出すことが重要。
豪州産牛肉については、グラスフェッドビーフを中心に生産頭数が回復し、比較的安定供給が見込まれる。
特に為替面で豪ドルが比較的穏やかに推移しているため、米国産に比べて価格優位性が際立ってくると考えられる。
豪州産アンガスビーフなど中高グレードのブランド牛を使用した、焼肉・ステーキなどの希少部位提案、味付け提案、夏場の需要に合わせた商品化を強化することが、価格上昇局面での売場の魅力を高める鍵となる。
例えば、「豪州産アンガスビーフバラ肉味付けプルコギ炒め用」など打ち出し、野菜キットなども品揃えするとより簡便性も高まる売場作りとなる。


【輸入豚肉】
これまで以上に国際的な需給バランスと通商政策の変化を踏まえた販売戦略が求められる。
特に注目すべきは、牛肉同様にトランプ大統領の政権復帰による、通商政策が再び保護主義的な方向へと舵を切る可能性が高まっていることである。
これにより、米国が輸出志向から内需重視に転じたり、対日輸出に関する条件が変更される懸念も出てきている。
実際、世界的に豚肉の需給はすでに逼迫しはじめており、中国をはじめとするアジア市場の需要回復も相まって、グローバルな争奪戦が激化している。
この中で、米国産豚肉にさらなる関税が課されるような事態になれば、日本のメーカーや輸入業者はコスト上昇を受け入れるか、調達先を変更する必要が出てくる。
その際に代替として注目されるのが、カナダ産やメキシコ産の豚肉であるが、これらの国もすでに中国や韓国などからの引き合いが強く、特に中国に対してアメリカは高い関税を提示しているため、需給バランス次第では「日本が買い負ける」状況が現実化する可能性も否定できない。
このような環境下では、精肉としても価格競争に依存するのではなく、輸入豚肉の価値を高める提案型販売への転換が不可欠となる。
たとえば、「米国産とんとろ」の薄切りを「焼きしゃぶ」として提案し、レモン果汁やおろしぽん酢などのあっさり系調味料と組み合わせた商品展開は、夏場の食欲が落ちる時期にもマッチし、差別化された販売が可能となる。
また、価格変動リスクの高い中で利益を確保するには、バックヤードの省力化も重要。
味付け済みのスライス肉や肉とタレを混ぜるだけのセット商品などを活用することで、加工コストの抑制と人手不足対策を両立させながら、付加価値の高い提案を検討しなくてはならない。簡便性・タイパ志向が高まる中で、ミールキットやワンパン調理向けの提案を組み込むことも、顧客満足と利益確保の両面で有効となる。
2025年の輸入豚肉市場は、単なる価格訴求では乗り越えられない環境にある。
世界的な争奪戦や通商リスクを踏まえたうえで、国産豚肉との差別化や味付け肉による独自性の発揮が、夏場の需要期を成功に導く鍵となる。
【輸入鶏肉】
世界的な鶏肉需要は2025年に2.5%から3%の成長が見込まれており、特に東南アジア、ラテンアメリカ、中東、アフリカなどの新興市場が牽引役となっている。
この成長は、鶏肉の手頃な価格と持続可能性への関心の高まりによるものである。
しかし、米国の関税政策が輸入鶏肉市場に影響を与えている。例えば、米国が中国からの輸入品に対して関税を引き上げた結果、中国は報復措置として、米国産の鶏肉や豚肉に15%の関税を課した。
このような関税の応酬は、世界的な貿易の流れを変え、主要な輸出国であるブラジルやタイからの鶏肉供給に影響を及ぼす可能性があります。
そのためには、鶏肉に関しても、仕入れや商品化、プロモーションも見直す必要があると考えられる。
① 多様な仕入れ先の確保:ブラジルやタイなど、主要な鶏肉輸出国からの安定供給を確保し、関税や貿易摩擦の影響を最小限に抑え、産地を増やすことでリスクを軽減させる。
② 商品の差別化:健康志向の高まりを受け、高タンパク・低脂肪の鶏むね肩肉など部位の拡充、海外の銘柄鶏肉などの付加価値商品を仕入れるなど新たな取り組みも検討していく。
③ プロモーションの強化:夏季のバーベキュー需要に合わせ、下味済みの鶏肉セットや即調理可能な商品の展開や、ミート惣菜などでの即食商品の強化による、消費者の利便性を高める。
【輸入ラム肉】
米国の羊肉生産者団体であるAmerican Sheep Industry Association(ASI)は、オーストラリアやニュージーランドからのラム肉輸入に対し、21%の追加関税を求めている。
この背景には、2024年にこれらの国からの輸入量が大幅に増加したことによる、米国内生産者の市場シェアが奪われる危険があったためと考えられる。
このような関税措置が実施されれば、日本に輸入されるラム肉の価格上昇も予想される。その対策としては、以下の観点も必要となる。
① 供給元の多様化:オーストラリアやニュージーランド、欧州などのラム肉調達を検討し、リスクを分散する。
② 高付加価値商品の展開:通常のラムではなく、サフォーク種など品種やグレードを変えたプレミアムブランドの展開やタレ漬け商品、小袋のタレを添付したりする付加価値商品の品揃えもポイントとなる。
③ 消費者教育の推進:ラム肉の栄養価(Lカルニチン)や調理法を紹介するキャンペーンを実施し、需要喚起を図る。
特に豪州産ラム肉では、MLAによる羊肉のプロモーションや販促資材の提供も行なっているので、しっかりと活用したい。
輸入肉の差別化を図るための「差別化提案」
畜肉の相場と為替による輸入肉市場の価格高騰が続く中、輸入肉を活用した「味付け肉」提案は、生活者・スーパーマーケット双方に大きなメリットをもたらす。
まず生活者にとっては、味付け肉は調理の手間が少なく、下処理不要で“焼くだけ”の手軽さが支持されます。
共働き世帯や忙しい家庭にとって、時短調理が可能で、タイパ(タイムパフォーマンス)を重視する現代のニーズに合致している。
また、既に味が付いているため、家庭では再現しにくい本格的な味わいが楽しめるのも魅力。そのため、美味しい調味料の組み合わせがポイントとなる。
一方、スーパーマーケットのバックヤードにとっても味付け肉の商品化は大きな利点がある。計画的に味付け肉は製造することが多いため、あらかじめ従業員への指示と冷凍商品の解凍など、事前に準備しておく事が可能となる。
パック詰めや味付け工程を標準化・効率化することで作業時間の短縮につながる。加えて、部門間連携による野菜とのセット提案やミールキット化などで、付加価値の高い売場作りが可能となる。
価格だけでは差別化が難しい現在、味付け肉による“調理提案型商品”の強化は、他店との差別化、売上拡大、利益改善のために不可欠な施策といえる。
具体的には、以下のような商品化で展開を行なうとよい。

豪州産アンガス牛バラ肉を使用し、味付けプルコギ炒め提案を行う。
牛肉は2mmでスライスしてタレと混ぜ合わせることで、上からかけるよりもボリューム感を出す。ポイントは「豪州産アンガス牛使用」を前面に打ち出し、品質で差別化を図る。
「プルコギ」は赤身の強い色のタレを用いることで鮮度感をだす。
トレーは内嵌合の蓋つきトレーを用いることで、液漏れすることなく、売場でも商品を立体的に陳列することが出来るようになる。
商品化は味付けだけでなく、野菜セットで “ワンパン調理”のタイパ訴求で、時短ニーズにも対応した商品も展開すると良い。

米国産とんとろを1.5mmの薄切りにし、「焼きしゃぶ」用として訴求する。
脂肪の旨みと食感を活かしつつ、あっさりレモン果汁やおろしぽん酢で“さっぱり”楽しめる夏向けメニューとして提案する。
切り落しにすると、焼肉の豚とろよりも量が多く見えるだけで無く、ボリューム感が増す。
レモンスライスを添えて商品化する。
試食販売や、POPを活用した、調理例の紹介。
家庭では味わえない「外食風焼きしゃぶ体験」で、競合量販店との差別化を図る。

比較的安く仕入れることが出来るタイ産若鶏肩肉とボイル済みジャガイモ角切りを組み合わせた、タレ漬け「ワンパン焼肉」提案を行なう。タレ漬け提案は、タレを混ぜるだけの簡単な商品であるが、混ぜ合わせる商材によって、値入れ率が大きく変わる。
特に、価格に大きく関わるお肉、3割程度混ぜ合わせるタレ、彩りにも必要な野菜の3拍子が揃うと、儲け商材となる。
消費者にとっても、下処理不要で焼くだけ簡単、タイパ重視の商材となる。スパイシーで食欲をそそる味付けとボリューム感で、家族向けメニューとして訴求力抜群。

豪州産ラム肉を「第4の畜種」として積極的に訴求する。
特製の小袋タレを添付することで、調理の手間を省き、手軽に本格ジンギスカンが楽しめる商品として展開する。
健康志向の「Lカルニチン、低脂肪高たんぱく」という栄養面の価値をアピールしつつ、バーベキューやアウトドア需要にも対応していく。
ラム肩肉は、3mmでやや厚めのスライスすることで、調理後にラム肉の食感を楽しむことが出来る。
トレーは銀色の丸皿を使用することで、ジンギスカンの外食を彷彿させる商品化となる。
より身近になった関税と為替問題
2025年の輸入肉を取り巻く環境において、特に注意すべき点は、為替相場の変動と各国の輸出動向による供給不安である。
円安傾向が続く中、米国産や豪州産の牛肉、カナダ産やメキシコ産の豚肉、ブラジル・タイ産の鶏肉すべてにおいて、輸入コストが上昇しており、価格転嫁による小売価格の高騰が避けられない状況にある。
また、トランプ政権による米国の貿易政策が変化すれば、再び関税措置が強化され、TPP等で享受していた関税引き下げの恩恵が揺らぐ可能性も否定できない。
加えて、中国・韓国をはじめとしたアジア諸国の旺盛な需要が続いており、日本が「買い負ける」リスクが顕在化している。
特に豚肉と鶏肉は、価格面での競争力を失えば即座に供給が逼迫する恐れがある。
よって、精肉部門においては、相場や需給動向を常に把握し、安定供給が可能な畜種・産地の選定、味付けや商品化による付加価値提案の強化、代替品の導入検討など、柔軟かつ迅速な対応が求められる。